小川 弥生 先生
北海道腎病理センター
病理と私

北大分子病理のホームページをご覧の皆様、こんにちは。
谷口教授のお計らいで、病理医の日常など簡単な体験談を書く機会を頂きました。折角紙面をいただいたので、忌憚ない病理への思いを書きたいと思います。
執筆は慣れてないので、読みづらい点もあるかと思いますが、ご容赦いただき、気軽に飛ばして読んでいただけると幸いです。
私は平成元年の医学部卒業生で、当初7年間臨床医として働いていました。そのあと、北大第一病理(現在 分子病理)に大学院生として進学し、病理診断と基礎研究を一からご指導いただきました。当時から、診断も研究も可能で自由で可能性に満ちた教室という印象でした。臨床一筋だった私は、論文を読むのも一苦労、研究の手法も理解に時間を要し、周囲の先生方には大変お世話になりました。大学院卒業後は、病理診断がしたいという思いが強く、臨床医の道を変更し、大学病院や総合病院で、病理解剖や外科病理診断を病理医の先輩たちから大変丁寧にご指導いただきました。卒業してから10年以上経過して始めた病理専攻医の指導は、客観的に考えて大変扱いにくかったのではないかと思います。今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、こんな私が、これから医学部を卒業して医療従事者の第一歩を始める若い方たちに情報を記すことができるとしたら・・・自身の経験から感じる臨床と病理の違い、私の視点からみた病理の魅力かしら、と思いました。
臨床医は、時間とともに変化していく患者さんの病態につねに対応することが必要で、特に卒業して数年は自身の時間を持つことが難しいです。時には一人の患者さんのことで一日中思考を巡らせても、最良の答えを導き出すことができず、辛い思いを引きずることがしばしばありました。でも患者さんの病態をずっと観察し、その方へのより良い医療を考えることはかけがえのない経験値となります。病状を計時的に共有することは、臨床医にしかできないことだと思います。
一方で、病理診断は、夜間に病理解剖で病院から呼ばれたり、迅速あるいは至急の診断が必要な標本と格闘したりしても、観察している個々の標本の時間は止まっており、時間的な猶予が臨床に比して残されています。つまり、自分のリズムで仕事をする余裕が医療の現場のなかで、若干残されている分野といえます。そして、少しの猶予が残されているだけに、有効な時間活用をして、質のよい、そして忙しい臨床により役立つ病理診断が期待されていると自負しています。
病理診断は、固定された標本に対して、知識と学びを活かして診断していきますが、よりよい臨床のパートナーとめぐり逢えた時、標本は臨床経過を演出して動き出します。病理解剖などで、詳細な経過や情報を臨床の先生から伺うと、数枚の標本から新しい理解が生まれてくることもあります。病理診断医としてとてもうれしい瞬間です。
また、病理医は臨床に寄り添いつつも、基礎に近い職場でもあります。Updateな基礎研究と臨床への応用にアンテナを張っておくことで、病理診断の質は変化し、実務への意欲もわきます。学会でテーマを頂き自身でまとめたり、若い先生方の研究を一緒に進行したりする機会は比較的多い印象を持っています。
ふりかえると、私は教室の先生方や、先輩、職場のみんな、そして同じ興味をもつ病理医にお世話になりながら、病理医というhappyな仕事を続けていることを実感しました。なるべく自分のリズムで時間を有効に活用して仕事をしたい方には是非お勧めします。そして病理のリズムをこれからも守るようにしていきたいとも思っています。
最後に、医学・医療の道に家族の協力は必須です。楽しく仕事をする背中には、きっと家族は理解を示してくれるでしょう。病理はいつも私の背筋をピンとさせてくれる大事な友人で、出会えて本当によかったです。
岩崎 沙理 先生
市立札幌病院病理診断科
一症例一症例で、臨床上解決されるべき問題に対する答えが求められています
 病理学というと、学生実習での細胞のスケッチを思い出す方が多いかもしれません。病理医は、絵合わせのように、教科書の写真と組織像を見比べて、似ているだけで「えい!」と診断しているのでしょうか。
病理学というと、学生実習での細胞のスケッチを思い出す方が多いかもしれません。病理医は、絵合わせのように、教科書の写真と組織像を見比べて、似ているだけで「えい!」と診断しているのでしょうか。
病理医の脳の中では、臨床経過と組織像から挙げられる沢山の鑑別疾患が渦を巻いています。教科書には、典型的な像だけでなく、非典型的なもの、類似する疾患などもよく見ると書かれています。病理医はそれらを脳にダウンロードしながら、さらに組織像を細かくみてながら、どの疾患の可能性がより高いか、選別を行っているのです。最初に思いついたとか教科書の絵と似ているというだけで、その診断に飛びつくようなことはしません。
私は一般病理医があまり好まない炎症性疾患が大好きです。炎症性疾患は、一般的に、疾患の数>組織パターンです(例: 補体遺伝子異常、SLE、HCV肝炎、その他多数の原疾患により、膜性増殖性糸球体腎炎の組織パターンを来す)が、近年は免疫チェックポイント阻害剤など治療薬に伴う炎症性疾患も加わり、非典型的な炎症性疾患が増え、難易度がさらに高まっています。沢山の鑑別疾患の中から、どこまで真実に近づけるか、一症例一症例、私達はそれに解を探すということを繰り返しています。このゲームの難しさ、面白さは、ぜひ解いて味わってほしいです。そして、導いた解答がどこまで正しいかどうかは、恐ろしいことに治療の経過が証明してくれます。病理医は標本をみて独り言を言っているような地味なイメージがあるかもしれませんが、標本を通しては体の中に降り立ち、病気そのものと対峙しているのです。
病理形態学は常にあらゆる遺伝子の異常やエピゲノムの変化の集大成です
病理形態学は古臭い学問でしょうか。何でも遺伝子で決まる時代になっているでしょうか。私はそうは思いません。これまで臓器別診療が叫ばれて臓器ごとに医学は専門化してきましたが、今は、例えば胃がんや乳がんとで同じ遺伝子異常があると、同じ治療薬が有効だと分かってきていて、臓器の垣根が必要ないこともあります。これは我々病理医からみると当たり前のことで、臓器が異なっていても、同じような形態像の腫瘍をみることはよく経験されるのです。病理医は、臓器別でなく、全身の疾患、腫瘍をみているからこそ、このような個別化診断、個別化診療の場面で貢献できます。病理診断ほど情報に溢れ、コストパフォーマンスがいい検査はないと、私はいつも考えています。近年では、病理医の手元にあるホルマリン固定パラフィン包埋組織から、より質の高い遺伝情報の抽出、それらと形態とを併せたより高度で踏み込んだ診断、特異な治療が可能になっています。そして、形態的な異常を説明できるような遺伝子等の異常というのが、これまでにないスピードで解明されつつあり、それらを合理的に結び付けられ、疾患概念を整理していけるどうかというところに、次世代の病理医が果たすべき役割があると思います。
病理医としてアカデミックに自由に働く
私は「病理にでも行けば」と、外科の教授の一声で出されましたが、病理は外科に比べて自由でアカデミックだと思います。そして、とにかく人が足りていません。病理医は、専門医の壁が外科専門医よりも高く、試験は難しいし、誤診しないで生きていけるほど楽ではありません。ですが、経験値が役にたつこともあり、年齢とともに順調に成長していける側面があります。70代、80代でも診断の仕事を楽しんで続けておられる先輩が沢山います。何より、臨床医とは異なり、患者さんの容態、麻酔科の都合、看護師さんの都合で、自分の時間を費やす必要がありません。自分のやりたいように仕事を組み立て、平日日中で仕事を終えることも十分可能です。それでも、四六時中患者さんに付き添っている主治医よりも、ずっとdeepに患者さんの病気の真実に近づき、診断を確定させ、根拠の上に正しい治療方針を決定づけることができます。不幸にも亡くなられた場合には、臨床診断がどこまで正しかったのか、病理解剖を行って、裁判官のように、詳細に検証することもできます。
私は3人子供を産み育てていますが、産休中は教室から出張などで対応してもらい、仕事を続けてこられました。高い専門性、仕事の面白さ、ワークライフバランスが両立する仕事だと思います。そして、どこまで診断に重きをおくか、研究など(私の場合、腎病理の勉強)に重きをおくかも、病理医により本当に様々で、可塑性のある職業と思います。分子病理学教室では、病理医として生きるための基礎体力をつけてもらい、いろんな可能性を教えてもらいました。病理医として病気の生の姿を診断する身には、研究を通して病気の捉え方を学ぶことや、医学論文を読みこなすことが、大変重要だったと今になって思います。
木内 静香 先生
北海道大学医学部 平成23年卒
細くとも長く、ライフイベントと両立して楽しみながら続けていきたい。
病理との出会い、10年間の継続
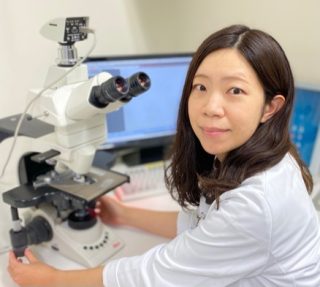
学部生時代、顕微鏡での形態観察が好きだったこと、病理学教室での実習の機会があったことなどから、病理が進路の候補となりました。幼少期から“町のお医者さん”に憧れて医学の道に進んだ経緯があったので、当初の理想とは異なる働き方を選択することに迷いもありましたが、診断を下すまでにじっくり考察することができる、書籍や論文での勉強と日々の診断が直結する、という仕事のスタイルに適性を感じ、この道を選びました。現在、私は市中病院の病理診断科に勤務し診断業務に専念していますが、卒後10年の間には大学院での基礎研究、子ども二人の出産・育児など大きなイベントがありました。そのような中でも、自分でペース配分しながら仕事のできる病理だからこそ、細くとも途切れることなく継続することができたように思います。
MD-PhDコースの選択
病理学を専攻するにあたり、MD-PhDコースへの進学を選択しました。これは6年生から学部の授業・国家試験受験と並行して大学院の研究活動を開始し、卒後は臨床研修を経ずに研究を継続、最短3年で大学院修了を目指すコースです。大多数が卒後すぐ臨床研修に進む中で、研修を先に延ばし大学院に進学することに不安や焦りもありましたが、長い医師人生の中、興味の強い時期に好きな学問・研究に没頭する期間があってもよいのではという思いもあり、この進路を選択しました。
大学院では実験的手法を用いた基礎研究と並行して病理診断のトレーニングを積みました。実験と診断、二つの領域を同時に学ぶのは当初は容易ではありませんでしたが、それぞれに習熟していくにつれ、両者を相互に役立てられる感覚を味わい、病理が“臨床と基礎の橋渡し”と表現される所以を実感しました。
病理診断は孤独?いいえ、たくさんの人との関わりがあります!
顕微鏡と睨めっこしながら黙々と診断、と思われがちですが、実は病理診断は多くのコミュニケーションの上に成り立っています。診断の難しい症例を上司・同僚と検討する、詳細な患者背景・検体情報を得るために臨床科主治医と連絡をとり場合によっては切り出しに立ち会ってもらう、病理診断を基にした治療方針検討のためカンファレンスを行う、といった多岐に渡る連携が病理診断の質を向上させます。病理に興味があるけれど、人と関わる仕事がしたいから…と考えている方、そのコミュニケーション能力は病理の分野でも大いに役立ちます。また、ディスカッションはちょっと…という方もご心配なく。日々の診断・検討会で無理なくトレーニングが可能です。
